NPO法人 アジア情報フォーラム
講演依頼、コラム執筆、国際交流企画など、ご相談は無料です
国際問題コラム「世界の鼓動」
生き返るか、自由主義
賛助会員 春海 二郎
(筆者は長年、在日イギリス大使館に勤務し、イギリス関係情報を独自に発信するサイト「むささびジャーナル」の運営をしている)
 むささびジャーナルがたびたび引用するThe Economistという雑誌の第一号が発刊されたのが1843年9月2日で、今年(2018年)は発刊175年にあたる。The Economistを発刊したのはスコットランド出身のジェームズ・ウィルソン(James Wilson)というビジネスマンだった。自由貿易を促進するためのキャンペーン誌として発刊されたのですが、19世紀半ばのヨーロッパとアメリカで支配的な考え方は保護貿易主義で、英国では「穀物法」(Corn Laws)と呼ばれる一連の法律によって外国からの農産物の輸入には高い関税が課せられていたりした。
むささびジャーナルがたびたび引用するThe Economistという雑誌の第一号が発刊されたのが1843年9月2日で、今年(2018年)は発刊175年にあたる。The Economistを発刊したのはスコットランド出身のジェームズ・ウィルソン(James Wilson)というビジネスマンだった。自由貿易を促進するためのキャンペーン誌として発刊されたのですが、19世紀半ばのヨーロッパとアメリカで支配的な考え方は保護貿易主義で、英国では「穀物法」(Corn Laws)と呼ばれる一連の法律によって外国からの農産物の輸入には高い関税が課せられていたりした。
穀物法に反対
The Economist発刊号の中でウィルソンは
穀物法は売り手が買い手に実際の価値よりも高くモノを売り付けることを目的として作られたものなのだ。
They are, in fact, laws passed by the seller to compel the buyer to give him more for his article than it is worth.
というわけで、穀物法に象徴される保護貿易というシステムは地主や農業資本家のような特権階級にのみ奉仕していると批判している。
 ジェームズ・ウィルソンが推進しようとした社会原則が自由貿易(free trade)、自由市場(free markets)、政府介入の制限(limited government)というもので、これらの考え方をまとめて「自由主義」(liberalism)と総称している。つまり「自由主義」というのは国の経済運営の在り方についての基本理念(central principles)であり、The Economist発刊以来の哲学であったわけです。
ジェームズ・ウィルソンが推進しようとした社会原則が自由貿易(free trade)、自由市場(free markets)、政府介入の制限(limited government)というもので、これらの考え方をまとめて「自由主義」(liberalism)と総称している。つまり「自由主義」というのは国の経済運営の在り方についての基本理念(central principles)であり、The Economist発刊以来の哲学であったわけです。
自由主義がけん引した170年
 The Economistが発刊された1840年代から今日までの175年間で、世界は大きく変わった。例えば世界全体の平均寿命は約30才から70才を超えるに至っている。いわゆる極貧状態(extreme poverty)で暮らす人間の割合は80%から8%へと下がっている。極貧よりは上という人間の数は、あの当時の1000万人から65億人にまで増え、識字率は16%から80%へと成長している・・・それらがすべて自由主義のお陰とは言わないまでも、19世紀半ばから21世紀の今日まで、人類を支配しようとした様々な思想(ファシズム、共産主義など)が失敗している一方で自由主義を堅持した社会だけは繁栄を謳歌してきたことは事実である、と。国や地域によって多少の違いはあるものの、いわゆる「自由民主主義」が欧米を支配し、さらにそこから全世界へと広がってきたのが人類の歴史である・・・と。
The Economistが発刊された1840年代から今日までの175年間で、世界は大きく変わった。例えば世界全体の平均寿命は約30才から70才を超えるに至っている。いわゆる極貧状態(extreme poverty)で暮らす人間の割合は80%から8%へと下がっている。極貧よりは上という人間の数は、あの当時の1000万人から65億人にまで増え、識字率は16%から80%へと成長している・・・それらがすべて自由主義のお陰とは言わないまでも、19世紀半ばから21世紀の今日まで、人類を支配しようとした様々な思想(ファシズム、共産主義など)が失敗している一方で自由主義を堅持した社会だけは繁栄を謳歌してきたことは事実である、と。国や地域によって多少の違いはあるものの、いわゆる「自由民主主義」が欧米を支配し、さらにそこから全世界へと広がってきたのが人類の歴史である・・・と。

一日1.90ドル(2011年の価値)で暮らしている人口が世界の総人口に占める割合<世界銀行>
が、最近どうも世界の流れがそれに反するような方向に向かっている・・・というわけで、2018年9月13日付の同誌では “Reinventing liberalism for the 21st century“(21世紀のために自由主義を作り直す)という特集記事を掲載しています。記事そのものは非常に長いものであり、手短にまとめることなど(むささびには)不可能です。この際、一か所だけ引用して、皆さまのディスカッションの材料にでもなってくれれば・・・と思う次第です。その気がおありの皆さまは原文をお読みになることをお勧めします。原文へのアクセスが困難な場合はご一報を。
自由主義の4原則
 The Economistは175年にわたって主として経済政策という意味での「自由主義」を掲げてきたわけですが、それを支える「世界観・人間観」について次のようにまとめている。
The Economistは175年にわたって主として経済政策という意味での「自由主義」を掲げてきたわけですが、それを支える「世界観・人間観」について次のようにまとめている。
1. 社会には対立(conflict)がつきものであり、それは将来も変わらないだろうし、変わるべきでもない。政治さえしっかりしていれば、対立は競争(competition)を生み、実のある議論(fruitful argument)にも繋がる。
2. 社会は常に動いている(dynamic)ものであり、良くなることもあり、悪くなることもある。自由主義者は社会を良くするために力を尽くすべきである(liberals should work to bring such improvement about)。
3. 自由主義者は権力(power)を信用していない。特に集中した権力(concentrated power)は信用しない。
4. 自由主義者は公的な存在としての個人を尊重(civic respect)するものであり、個人の私生活上の権利、政治的権利、財産権を尊重することを主張する。
このうち1)~3)については、The Economist発刊の時点でも存在していた感覚であると言えるけれど、4)で言われている「公的な存在としての個人を尊重」というのはごく最近の考え方だと思います。NPOとかNGOのような考え方で、運営資金にしても国家からの支援(税金)ではなく自発的な個人による献金を基本にする。いまから約20年前に登場したトニー・ブレアの労働党政権が掲げた「第三の道」(The Third Way)という理念がこれに極めて近いし、当時はThe Economisも大いにテコ入れした思想だった。国家中心主義でもなければ、国家の存在そのものを否定するような極端な個人中心主義でもない、かと言って単なる「いいとこどり」の折衷主義でもない・・・そんな思想のはずだった。
歴史の終わり・・・
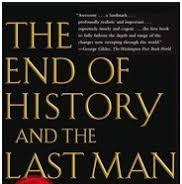 その自由主義者たちが推進したのが、貿易のグローバル化や人間の往来(migration)の自由であり、そのような政策によって推進されたのがアメリカをリーダーとする「自由主義的な世界秩序」(liberal world order)だった。第二次世界大戦以後のことです。そして1990年代初期のソ連の崩壊によって、社会組織の優劣競争の点で自由主義は最終的な勝利をおさめた・・・と思われた。その象徴とも言えたのが、1992年に出たフランシス・フクヤマの『歴史の終わり』(The End of History and the Last Man)という著作だった。この本のメッセージは次のように説明されている。
その自由主義者たちが推進したのが、貿易のグローバル化や人間の往来(migration)の自由であり、そのような政策によって推進されたのがアメリカをリーダーとする「自由主義的な世界秩序」(liberal world order)だった。第二次世界大戦以後のことです。そして1990年代初期のソ連の崩壊によって、社会組織の優劣競争の点で自由主義は最終的な勝利をおさめた・・・と思われた。その象徴とも言えたのが、1992年に出たフランシス・フクヤマの『歴史の終わり』(The End of History and the Last Man)という著作だった。この本のメッセージは次のように説明されている。
自由主義的民主主義こそは世界にとって最終的な統治体制であり、人間による思想的な闘いの終わりを意味するものとなった。
Liberal democracy is the final form of government for the world, and the end of human ideological struggle.
というわけで、自由主義を基盤とする民主政治が政治体制の最終形態であり、安定した政治体制が構築されるため、政治体制を破壊するほどの戦争やクーデターのような歴史的大事件はもはや生じなくなると考えられた。
エリートへの反乱
 が、The Economistによると、このような社会体制においても置いてきぼりを食ったと考える人間がおり、自由主義的な体制の先頭に立つ「自由主義エリート」(liberal elites)に対して攻撃を加えるようになった。自由主義は時代の変化に適応する能力という点では優れていたかもしれないけれど、外国からの移民の流入などで職を失った(と考える)労働者階級にとって、自由主義は自分たちを犠牲にして綺麗ごとを並べ立てるエリートたちの思想としか映らなかった。英国におけるBREXITの勝利、アメリカにおけるトランプの勝利はその象徴的な出来事だったけれど、The Economistによると、自由主義社会自体が生んだ反乱現象とは別に、現代社会においては事実上の独裁といえるロシアや一党独裁の中国も自由主義の敵ということになる。
が、The Economistによると、このような社会体制においても置いてきぼりを食ったと考える人間がおり、自由主義的な体制の先頭に立つ「自由主義エリート」(liberal elites)に対して攻撃を加えるようになった。自由主義は時代の変化に適応する能力という点では優れていたかもしれないけれど、外国からの移民の流入などで職を失った(と考える)労働者階級にとって、自由主義は自分たちを犠牲にして綺麗ごとを並べ立てるエリートたちの思想としか映らなかった。英国におけるBREXITの勝利、アメリカにおけるトランプの勝利はその象徴的な出来事だったけれど、The Economistによると、自由主義社会自体が生んだ反乱現象とは別に、現代社会においては事実上の独裁といえるロシアや一党独裁の中国も自由主義の敵ということになる。
改革精神の復活を
ピンチに立たされた「自由主義」ですが、ではその再生のためには何をするべきだとThe Economistは考えているのか?自由主義が個人の尊重を絶対的な理念としており、それが故に人間が作る社会には対立がつきものであると考えるので、マルクスが提唱した社会主義的な進歩の思想を「空想的」(Utopian)として否定する。その一方で保守主義者(conservatives)に対しては、安定と伝統(stability and tradition)ばかり重視しすぎるとして退ける。自由主義はあらゆる意味における「進歩」(progress)というものを重視する。その意味において常に社会変革を求める存在であり
現代の自由主義に必要なのは、エリートとか体制というものと同一視されないことであり、その意味において元来持っているはずの改革精神を復活させるということである。
Today liberalism needs to escape its identification with elites and the status quo and rekindle that reforming spirit.
と言っています。