NPO法人 アジア情報フォーラム
講演依頼、コラム執筆、国際交流企画など、ご相談は無料です
国際問題コラム「世界の鼓動」
オリンピックを古代に戻そう!
賛助会員 春海 二郎
(筆者は長年、在日イギリス大使館に勤務し、イギリス関係情報を独自に発信するサイト「むささびジャーナル」の運営をしている)

オリンピック関連の記事をいくつか紹介します。
 まず、最近、2024年の開催都市として立候補を断念したアメリカのボストンですが、ボストン・グローブ紙のコラムニスト、ジョアン・ベノッチ(Joan Vennochi)は8月1日付の同紙に「古いボストンにさよならを言おう」(Say farewell to old Boston)というエッセイを載せています。彼女のいう「古いボストン」とは、不動産開発業者、建設業者、PR会社およびこれらと利害関係をともにする政治家や「市の偉いさんたち」(city’s elite)・・・要するに五輪招致に血眼になっていたもろもろの関係者のことです。中には野球のボストン・レッドソックスのスターも含まれている。
まず、最近、2024年の開催都市として立候補を断念したアメリカのボストンですが、ボストン・グローブ紙のコラムニスト、ジョアン・ベノッチ(Joan Vennochi)は8月1日付の同紙に「古いボストンにさよならを言おう」(Say farewell to old Boston)というエッセイを載せています。彼女のいう「古いボストン」とは、不動産開発業者、建設業者、PR会社およびこれらと利害関係をともにする政治家や「市の偉いさんたち」(city’s elite)・・・要するに五輪招致に血眼になっていたもろもろの関係者のことです。中には野球のボストン・レッドソックスのスターも含まれている。
ベノッチによると、五輪招致に反対した人びとのなかには「古き良きボストンが壊される」ことを快く思わない年寄りエリートたちもいたけれど、反対運動の中心だったのは、FacebookやTwitterのようなソシアルメディアを駆使して運動を展開した “No Boston Olympics“ という若者のグループだった。彼らのメッセージは “thinking smart” で、オリンピックではボストンの将来は築けないと訴えた。で、最初は誘致に乗り気だった市長も米国五輪委員会(USOC)から、開催予算がオーバーした場合はボストン市が追加分を負担すべしとする契約を迫られてノーと言わざるを得なかった。
 次に紹介するのが今年2月28日付けのThe Economistに出ていた “Sporting mega-events: Just say no”(スポーツ関連の巨大イベントなんて止めたほうが利口だ)という記事です。これは実はアメリカのアンドリュー・ジンバリスト(Andrew Zimbalist)というスポーツ経済学者(そんなものがあるんですね)が書いた「極限のサーカス」(Circus Maximus)という本の紹介です。この本のサブタイトルは
次に紹介するのが今年2月28日付けのThe Economistに出ていた “Sporting mega-events: Just say no”(スポーツ関連の巨大イベントなんて止めたほうが利口だ)という記事です。これは実はアメリカのアンドリュー・ジンバリスト(Andrew Zimbalist)というスポーツ経済学者(そんなものがあるんですね)が書いた「極限のサーカス」(Circus Maximus)という本の紹介です。この本のサブタイトルは
The Economic Gamble Behind Hosting the Olympics and the World Cup
オリンピックとワールドカップを主催するについての経済的ギャンブル
となっている。
オリンピックやワールドカップのような世界的なイベントを開催するには大変なコストがかかる。しかし開催都市や主催国はこれらのイベントを通じて世界中の注目の的になり、観光収入は莫大なものになるであろうし、イベントを機にインフラ整備も行われたりして、その経済的な効果も計り知れないほど大きい。だから・・・というのが、これらのメガイベントを招致する人びとの考えですね。
実際、2012年のロンドン五輪が生み出した収入は、テレビ放映権、入場券販売、さまざまなライセンス使用料とスポンサーシップなどを併せて520億ドルだったそうです。これが全部、ロンドンの懐に入るのであれば英国にとってもロンドンにとっても万々歳だった。特にロンドンのように、もともとホテルや競技場のような「インフラ」はそれなりに整備されているような都市の場合、既存のものを利用すれば十分に黒字であったはずである、と。
が、ジンバリストによると、ここ数十年、五輪収入についてのIOCの取り分がすごいのだそうです。例えばTV放映権収入の半分以上がIOCに行ってしまう。1960年~1980年のころの五輪ではIOCの取り分は4%~10%に過ぎなかったのに、です。観光収入というけれど、北京(2008年)の場合もロンドンの場合も五輪の年の観光客は前の年に比べて減っているのだそうですね。TV放映権収入は、五輪収入全体の半分を占めるのですが、1964年の東京五輪の場合、160万ドルで、その殆どが東京への収入になったのですが、2012年のロンドン五輪の場合、収入は25億6900万ドル、うち51%はIOCの懐に入ったというわけです。
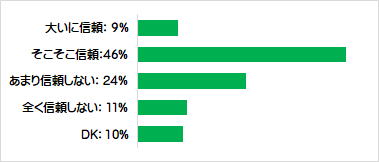 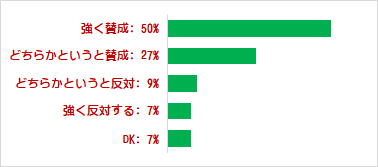 |
FIFAの場合、ワールドカップのゲームそのものの実施予算はFIFAが出すということになっているのだそうですね。しかしワールドカップであれ、オリンピックであれ、最もお金がかかるのは、ゲームそのものではなく、会場建設やそれに伴う交通網のようなインフラ建設でこれはすべてホスト側の負担となる。FIFAもIOCも表立って新しい施設の建設を求めることはないけれど、これまでのホスト選択を見ると、やはり見た目にも派手な競技会場を提示した都市や国が選ばれている事実は否定できない、とThe Economistの記事は指摘します。
7月28日付のワシントン・ポスト紙のサイトにメリーランド大学で都市計画を研究するジョン・ショート教授の寄稿エッセイが出ているのですが、その中に驚くような数字が出ています。すなわちオリンピック関連の施設建設に伴って立ち退きをさせられた人の数です。これまでの20大会の合計が2000万人だそうです。1大会平均100万人ということです!例えば1988年のソウル五輪の場合、低所得者層が暮らすエリアに関連施設が作られたため75万人が「移住」させられ、アトランタ五輪(1996年)のときは黒人街の住人3万人が立ち退きを余儀なくされた。すごいのは2008年の北京五輪で、125万人が自分の住んでいるエリアを離れたのだそうです。
 |
 |
||
| 左は北京五輪のビーチバレー会場(五輪開催当時)、右は現在の様子 | |||
アンドリュー・ジンバリストによると、巨額の税金を使って作られた施設もイベントが終わってしまうと、「無用の長物」(white elephants)と化してしまうケースがあまりにも多い。アテネ五輪(2004年)のバレーボール会場は、ホームレスがたむろする施設になっているし、ソフトボール会場は樹木が生え放題、北京五輪(2008年)自転車競技会場は草ぼうぼう、つい昨年(2014年)ブラジルで行われたワールドカップの会場の一つなどは、4万人収容のはずなのに、現在使っているのは観客が1500人程度という「二軍戦」だけという具合です。
こうした状況ではさすがに立候補する国も都市も減っている。例えば2004年の五輪ホストにアテネが選ばれたときは12都市が立候補していたけれど、2020年(東京)の場合はわずか5都市、2022年の冬の五輪(北京)の場合は、最初は立候補する予定だったオスロー(ノルウェー)が降りてしまったので、立候補地は北京とカザフスタンのアルマティという都市だけだった。2028年が前回のアムステルダム五輪(1928年)から100年目にあたるというので、オランダ政府も立候補を検討中なのですが、とてつもないコストを考えると「五輪は非民主主義の国が国威発揚のために行うもの」という意見も出ており話が進まないのだそうです。
というわけで、アンドリュー・ジンバリストなどは、IOCもFIFAも新しい競技会場の建設を奨励するかのような態度を改めて既存の会場の利用を奨励することが肝心だと言っている。ただ前出のメリーランド大学のジョン・ショート教授はさらに「画期的」と思われる提案をしている。
We should host the Olympics in the same place every time
オリンピックのホストは常に同じ都市であるべきだ。
つまりオリンピックに関しては世界の都市における持ち回り開催というアイデアを止めにして、どこか一か所を「オリンピックの町」に決めて、夏の五輪といえば常にその町でのみ開かれることにするというものです。もともと五輪が持ち回りで開催されるようになったのは、近代オリンピックが始まった1896年(アテネ)のことであり、それまでの「古代オリンピック」常にギリシャのオリンピアで開かれていたではないかというわけです。言えてる!